古物商許可を取得するには、住民票や身分証明書などいくつかの添付書類が必要ですが、
令和元年12月14日以降の申請からは、
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行により、「登記されていないことの証明書」の添付が不要になりました。
単に提出しなくて良くなったということではありません!
提出しない代わりに、「誓約書」の内容が変更されています。
古い誓約書では受付してもらえませんので、ご自身で申請される方は警察署に新しい申請書をもらいに行くのを忘れないでくださいね。
ここからは、どうして法改正がされたのかを簡単に解説していきます。
「登記されていないことの証明書」とは?
そもそも「登記されていないことの証明書」とは、どういったものでしょうか?
これは成年後見制度の利用者を登記(登録)している「後見登記等ファイル」に登録されていないことを証明する書類です。
と言われても、よくわからないですよね・・・。
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下してしまった人(成年被後見人等)のサポート役(成年後見人)を家庭裁判所から専任してもらう制度です。
判断能力が低下してしまった人が、セールスマンに言われるがままに高額な商品を購入させられてしまったり、不動産を安値で売却してしまったのでは困ってしまいます。
成年後見制度を利用すると、サポート役である「成年後見人」の同意がない法律行為は取り消すことができるので、成年被後見人等を保護できるようになります。
「登記されていないことの証明書」は、「成年後見制度を利用していないので、成年被後見人等ではないですよ。」ということを証明する書類なのです。
何故、登記されていないことの証明書が必要なの?
古物商許可申請で「登記されていないことの証明書」が必要だった理由は、古物営業法の許可の基準の欠格要件に「成年被後見人若しくは被保佐人・・・ではないこと」と明記されていたからです。
許可を取得するためには、自分が欠格要件に該当しないことを証明しなければなりません。そのために「登記されていないことの証明書」の提出が必要でした。
法改正へ
今回は、古物商許可を例に「登記されていないことの証明書」が不要になった。という話をしていますが、古物商以外にも、警備員や公務員や会社の役員等にも同様の欠格要件が法律に明記されていました。
もちろん、成年後見制度を利用している人でも、問題なく働くことができる人もいます。
それなのに、多くの法律で「成年被後見人、被保佐人・・・」を欠格要件として、一律に廃除する規定が設けられていたのです。
今まで問題なく働いていたのに、「財産管理が不安だから成年後見制度を利用しよう。」そう思って成年後見制度を利用したら、欠格要件に該当することを理由に許可を取り消されたり、職を失ってしまうのです。
なんだか納得いかないですよね。これでは成年後見制度の利用も躊躇してしまいます。
こうした背景もあり、成年被後見人等であることを理由に、一律に資格等から廃除する仕組みを改め、それぞれで個別的・実質的な審査を行うために法律が見直され、欠格条項の見直しがされたのです。
2019/12/14以降に古物商許可の申請をする方へ
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行により、「登記されていないことの証明書」の添付は不要になりました。
代わりに「誓約書」の内容に変更がありますので、警察署で新しいものを調達する必要がありますのでご注意ください。

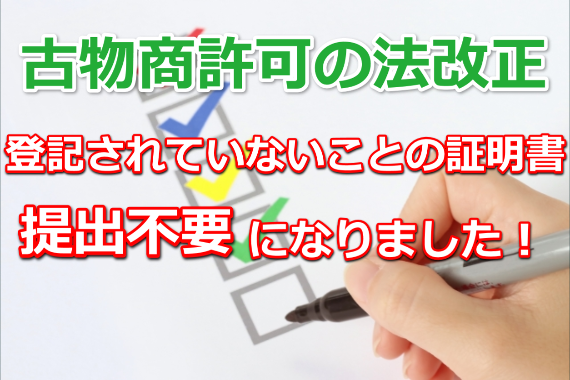

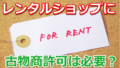
コメント